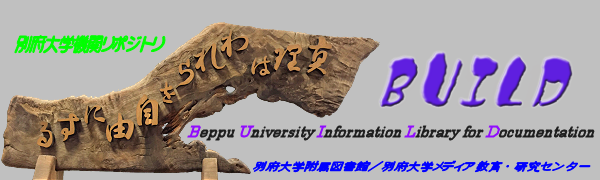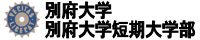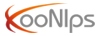詳細
閲覧数:1312
| ID | sk04306 | |||||||||||||||
| アイテムタイプ | Article | |||||||||||||||
| このアイテムを表示する |
|
|||||||||||||||
| タイトル | 「月と太陽」の未習/既習児童における月の満ち欠け理解の発達 | |||||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||||
| 著者 |
|
|||||||||||||||
| 出版地 | 別府 | |||||||||||||||
| 出版者 | 別府大学短期大学部初等教育科・保育課児童学会 | |||||||||||||||
| 日付 |
|
|||||||||||||||
| 形態 | ||||||||||||||||
| 上位タイトル |
|
|||||||||||||||
| 識別番号 |
|
|||||||||||||||
| 抄録 | 小学3年生から6年生を対象に,月の満ち欠けの理由(仕組み)について,子どもたちが どのような認識を持っているのかを調査した結果,月の満ち欠け学習前の児童も,潜在的に はさまざまな誤概念を持っていることが確認された。特に学年が上がるにつれて,①子ども たちの中で月の満ち欠け理由について正しそうな説明と,そうではない説明が徐々にはっき りと識別されるようになること,②「月の変形や変色」による説明は相対的に評価が低下し, 「地球の影」や「地球の自転・公転」「太陽光のあたり方」による説明(誤概念)が,正しい と評価される傾向が高まることが明らかになった。月の満ち欠け学習後間もない6年生の半 数近くは,科学的な説明に近い説明ができるようになるが,多くの子どもが依然として「太 陽光のあたり方」によって説明することも示された。 |
|||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| NDC | ||||||||||||||||
| 言語 |
|
|||||||||||||||
| 資源タイプ | text | |||||||||||||||
| ジャンル | Departmental Bulletin Paper | |||||||||||||||
| 著者版フラグ | publisher | |||||||||||||||
| Index |
|
|||||||||||||||
| 関連アイテム | ||||||||||||||||