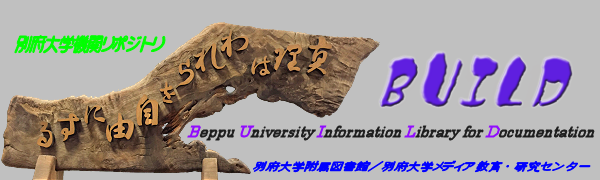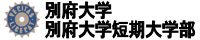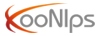|
XooNIps検索
インデックスツリー
|
詳細
閲覧数:1526
| ID |
M1513004 |
| アイテムタイプ |
Article |
| このアイテムを表示する |
| 本文 |
M1513004.pdf
| Type |
: application/pdf |

|
| Size |
: 271.6 KB |
| Last updated |
: Jun 19, 2017 |
| Downloads |
: 978 |
Total downloads since Jun 21, 2017 : 978
|
|
|
|
|
| タイトル |
大分県における近世灯籠研究
|
| 別タイトル |
|
| 著者 |
|
種生, 優美
|
|
別府大学大学院文学研究科文化財学専攻
|
|
| 日付 |
|
| 形態 |
|
| 上位タイトル |
|
| 識別番号 |
|
| 抄録 |
石造物というものは石仏や五輪塔、宝篋印塔、板碑など様々な種類がある。その中でも石灯籠は各地でみることができる。石灯籠は、538 年に百済から仏教とともに日本に伝えられたことが起源であり、御加護をより一層強く願うために神前に灯りをともすことを目的として祈願者から奉納されたものである。
石灯籠研究というものは天沼俊一を初めとして様々な分野の研究者によって行われてきているが、調査対象である石灯籠のデータが圧倒的に少ないのが現状で、近世の石灯籠は、調査対象数が非常に多く、調査を行うには時間がかかるとされ、地方自治体などではあまり近世の石灯籠は調査研究されてきていない。そこで石灯籠の型式がどう変化したのか、地域的特色はみられるか。またなぜ竿部の形式が撥形へと変化したのか、2 基 1 対の形にな ったのはなぜか。この 4 点を中心に見ていきたい。 |
| キーワード |
|
| NDC |
|
| 言語 |
|
| 資源タイプ |
text |
| ジャンル |
Article |
| Index |
|
| 関連アイテム |
|
|